都市計画法
目次
- 都市計画法
- コメント
| 区域 | 期間 | 更新 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 | すでに市街地を形成している区域もしくは、10年以内に優先的かつ計画的に市街地を図るべき区域 |
| 市街化調整区域 | 市街化を抑制すべき区域 | |
| 非線引き区域 | 上記以外の都市計画区域 | |
| 都市計画区域以外 | 準都市計画区域 | 将来市街化が可能であるが、放置すれば開発に支障が出る区域 |
| 無指定区域 | 都市計画区域と準都市計画区域以外の区域 |
都市計画法に基づく都市計画を行うに当たって、区域区分を覚えなければなりません。内訳は上記の表のとおりで、日本全体で都市計画区域に指定されている土地は約25%ほどと言われています。
都市計画区域は、原則として都道府県が、準都市計画区域は、都道府県が指定します。
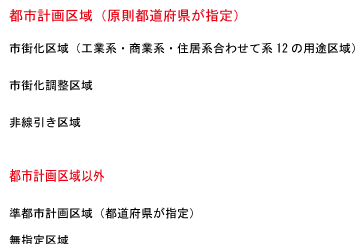
指定された区域で都市開発を行う場合、まず、各市町村が都市施設(道路、公園、下水道など)を作りますが、この際、建築物の建築についてのみ都道府県知事の許可が必要になります。
個人が開発行為(建物を建築したり、特定工作物を建設するために土地の区画や形質を変更すること)を行う場合は、都道府県知事の許可が必要です。 ただし、開発行為でもある一定の条件をみたす場合(市街化区域内の1000平方メートル未満など)は、許可は必要ありません。 よって、市街化区域内に、個人の家を建てるくらいのことは何ら問題ありません。
また、市街化区域内で、面積が大きかったとしても、そこが農林漁業の建築物や農林漁業者が自宅を建築するための開発行為の場合であれば許可は不要です。
市街化区域内で開発行為を行うためには、都道府県知事の許可が必要ですが、その時の申請書には、開発行為に関係のある公共施設の同意書を添付しなければなりません。 申請内容は、都道府県知事により、都市計画法33条の基準(技術基準)に照らし合わせて審査されます。
市街化調整区域内で開発行為を行うのであれば、技術基準に加えて、都市計画法34条の基準(立地基準)がダブルで適用されます。 この立地基準のせいで、調整区域には安易に住宅を建てることができないのです。
登記事項証明書にはこの事項は載らないので、各市町村のHPで確認する。
- こうのとりっぷ ・・・テーマ変更→都市計画→都市計画から調べられる。(検索したい場所をクリックすることでその場所が都市計画区域内か、区域区分、容積率や建蔽率も調べることが可能)
- 群馬県の市街化調整区域マップ
市街化調整区域と市街化区域については、固定資産税明細書の評価額の項に「調」や「市」等が書いてあることもあり、それでも識別もできるのでこれを使うのがベスト。
市街化調整区域に家を建てることが出来る条件として、
- 都市計画法第34条11号:市街化区域との境界付近のような土地であれば建築可能。立地基準。
- 都市計画法第34条12号:建築予定地と同じ市内の市街化調整区域に連続して20年以上住んでいる親族(6親等以内)が他にいる場合は例外として建築可能とする法律だが、昭和45年の線引き前から建築予定地である市街化調整区域を自己または親族が所有している場合は市街化調整区域に現在居住していることや20年以上の要件はない(詳細は法第34条12号(線引き前所有と集落内分家)の要件)。立地基準。
- 都市計画法43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限):市街化調整区域には原則として住居を建築することはできませんが、市街化区域から1km圏内や市街化区域まで4mの道路がつながっている場合などは申請により建築可能になる。34条の基準を守り建築するための建築許可。
- 農地転用:地目が田や畑になっている不動産を農地という。市街化調整区域にある農地を売るには、農業委員会の許可が必要。農地を農地以外の用途に変える事を「農地転用」という。地目が雑種地でも取り扱い自体は農地として扱われる。 「農林漁業を営む者の居住用建築物」は開発許可が不要です。そのため、農家の人なら自宅を普通に建てることができます。
がある。第34条11号と12号はどちらか一方を市町村がその場所に指定していて、どちらを使うかどうか、どちらかが使えるかどうかは市町村の建築担当課に聞かないとわからない。
不動産
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
- << 前のページ
- 次のページ >>

